
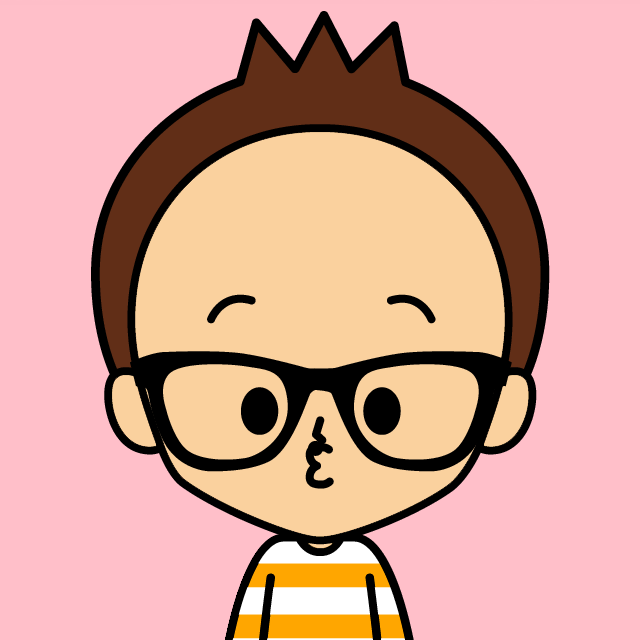
「係長の自分が今さら辞めるなんて、無責任だろうか……」
「引き継ぎも不十分だし、残された部下のことを思うと申し訳ない」
責任感が強く、職場を支えてきた人ほど、そんな重圧に押しつぶされそうになっているはずです。かつての私もそうでした。
私は以前、ブラック企業で退職を申し出た際、上司に退職届を突き返された経験があります。
「新入社員から育ててやったのにもったいない」
「期待している。今辞めるのは逃げだぞ」
そう言われ、自分の意思が完全に無視された時の、あの頭が追いつかない絶望感は、今でも忘れられません。
しかし、その後の職場で出会った「Kさん」という係長の姿を見て、私の考えは180度変わりました。
しかし、係長のような中間管理職が退職することに問題は全くありません。
私が働いていた職場の係長が会社を退職した事例を紹介します。
管理職だから会社を辞めないと言うことはありません。
近年では、管理職候補であってもキャリアチェンジや副業を選ぶ人が増えています。
今回は実際に係長を辞めたKさんの事例をもとに、「係長退職」のリアルを解説します。
衝撃だった係長・Kさんの去り際。自分を最優先に守る「強さ」
私の職場にいた係長のKさんの退職した事例を紹介します。
Kさんは決して、周囲から慕われる「理想のリーダー」ではありませんでした。
退職した係長Kさんのプロフィールと背景
年齢:30代後半
職種:製造部門
役職:係長(部下10人)
勤務年数:約5年 中途入社
性格:上下関係なく、意見の食い違いには反論する
評価:仕事は出来るが、周りからは煙たがられている
Kさんは入社後コツコツと成果を出し、30代後半で係長に昇進しました。
係長に昇進し、仕事は出来るが周りからはいい評価はされていない係長でした。
ズバズバ言って上司を黙らせる。徹底した自己防衛の流儀
朝礼で設備の故障報告があれば、上司に対して「その対策じゃ明日も止まりますよ」とズバズバ切り込み、相手を黙らせてしまう。
自分に非があれば「これは部下にやらせておきます」と、徹底して自分を守り、責任を周囲に逃がす。
一見すると冷徹で、自分勝手な人に見えたかもしれません。
係長は部門外との連携が必要になってくるため、他部門への自分のアピールは評価に直結します。
但し、過剰なアピールや、周囲への批判がKさんが煙たがられる理由でした。
嫌われてもいい?「辞めやすい空気」を自分で作るスキル
彼はある意味、組織の雰囲気に染まりきらない「最強の個」でした。
「会社にどう思われるか」よりも「自分がどうしたいか」を貫く。
周囲からの意見に納得出来なければ黙って従うことはなく、自分の意見は何としてでも押し通す係長でした。
そんな彼が退職を決めた時、引き止められる隙など1ミリもありませんでした。
Kさんが退職後の職場はどうなったか?
Kさんが辞めたら、現場はパニックになるのではないか?
私はそう思っていました。
「またかよ」と言いながらも、淡々と業務を回す部下たち
しかし現実は違いました。残された部下や班長たちは、「またかよ……」と不満をこぼしながらも、淡々と業務をこなしていきました。
日頃から係長のKさんに振り回されていた部下達だったので、退職することについてもあきれながら受け入れていました。
係長が退職したことをネガティブに考える人よりも、ポジティブに考えている人の方が多い印象でした。
リーダー不在が「新しい働き手」を成長させるという皮肉
驚くほど、普通に職場は回ったのです。
この時、私は気づきました。
「自分がいないと回らない」なんていうのは、真面目な人が勝手に背負い込んだ幻想に過ぎないのだ、と。
係長が辞めたことを補うために、個々の仕事のレベルが上がり、職場としてはいい方向に変化しているようにも感じました。
Kさんの退職までの時系列
係長のKさんが退職するまでを時系列でまとめてみました。
副業がうまくいった【退職半年前】
在職中に始めた副業が軌道に乗り、本業の収入に匹敵するようになったことが大きな転機でした。
退職決定~引継ぎ【退職1か月前】
退職の1か月前に、係長の上司である課長に退職の意思を伝え、その後は引き継ぎマニュアルを作成し、後任者に指導したことで大きなトラブルはありませんでした。
仕事が出来るKさんだったので、退職を伝える前から少しずづ引継ぎ資料の準備や、部下の教育の準備を進めていたのかもしれません。
係長になった後に転職することはメリットがある
係長にもなると会社を辞めにくいとも思うかもしれませんが、辞めるメリットもあります。
中間管理職として仕事をバリバリやってきた人は、転職時に大きく評価されます。
マネジメント経験を活かした転職ができれば、年収アップも可能です。
- 管理職経験が評価される
- マネジメントを経験活かして転職先の幅が広がる
- 管理職として転職することで年収アップを狙える
転職にはリスクがあるので、メリットだけではありません。
デメリットもあります。 デメリットの大きな部分は、思い描いていたものと違うということです。
- 転職後に思っていた仕事と違う仕事に担当させられる
- 転職先の方がストレスを多く感じる
- 見知らぬ部下を扱いにくい
- 今まで経験したスキルを活かして仕事が出来ない
転職にデメリットがあるのは事実ですが、このデメリットは係長からの転職ではなくても当てはまります。
会社の情報を良く知っておくことでリスクは回避できます。
係長を辞めたいと思っているのならば、まずは自分がどんな会社に転職出来るかを調べてみませんか?
「働き蟻の法則」が証明する。あなたの代わりは必ず現れる
なぜ、重要なリーダーが抜けても組織は止まらないのでしょうか。そこには「働き蟻の法則(2:8:2の法則)」という科学的な理由があります。
『自分は人よりも仕事ができるから辞めたら皆が困るはず』
『自分が辞めると周りに今まで自分が抱えていた仕事が分散されるので迷惑をかけてしまう』と思っていても実際はそんなに残された人が困ることは有りません。
個人の能力だけではなく、組織というものがそういう仕組み(2:8:2)でできているからです
 2割のリーダーが消えても組織が止まらない科学的理由
2割のリーダーが消えても組織が止まらない科学的理由
集団のうち、よく働くのは全体の2割。
その「2割のリーダー」が取り除かれると、残ったメンバーの中から、その穴を埋める新しいリーダーが自然と現れるようにできています。
会社組織は正常にまわります。仕事がバリバリ出来る人にとっては少しだけ残念な情報かもしれませんがそれが事実です。
あなたが辞めることは、部下への「最高の教育」になる
あなたが責任を感じて居座り続けることは、皮肉にも下の世代の成長機会を奪っているとも言えます。あなたが去ることで、現場は新しい形に進化するのです。
働き蟻の法則と同じように、あなたが出来る蟻だったとしても、あなたが抜けても同じ割合に戻ることになります。
あなたが抜けた穴は、他の人が成長することで補ってくれます。
仕事を辞めたいと思ってなかなか辞められない方、強引な引止めに遭っている方にこそ、この働き蟻の法則を知って頂きたいです。
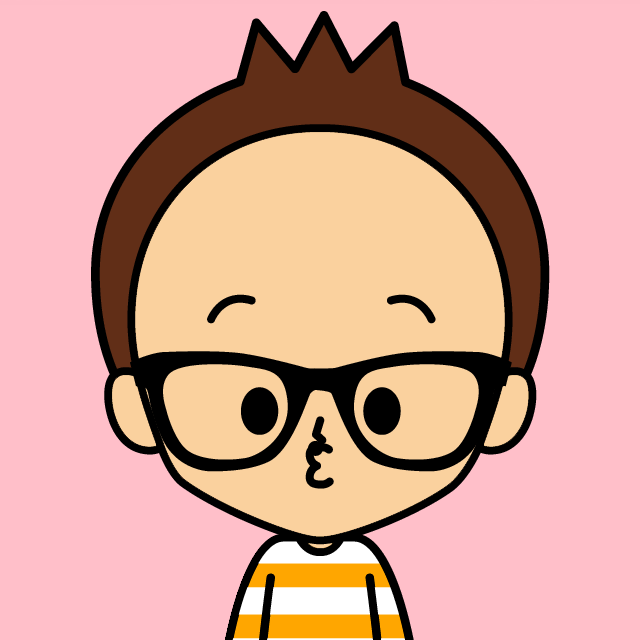
もう一度、自分の人生のハンドルを取り戻そう
退職したいけど、周りのことを考えると踏み出すことが出来ないと思う人でも、退職しても組織で仕事が回っていくことが理解いただけたと思います。
最低限の引き継ぎをしたら、あとは振り返らなくていい
それなりの引き継ぎや、後任への配慮。あなたはこれまで、十分に責任を果たしてきました。これ以上、自分の人生を会社に捧げる必要はありません。
話が通じない相手には「退職代行」という戦略的撤退を
もし、かつての私のように「話の通じない相手」に捕まって絶望しているのなら。プロの力を借りて、強制的に「相手に諦めてもらう」のも立派な戦略です。
「辞めたい」という部下の意思を無視し、人生を縛り付ける会社の方が、よっぽど無責任です。Kさんのようにドライに、自分を大切に。次は、あなた自身の人生のために、そのエネルギーを使ってください。
自分の力では会社を辞めることが不安な人のために退職代行サービスと言うものが存在します。
私はブラック企業を強引に辞めることが出来ましたが、退職するまでは『本当にこの会社を辞めることができるのだろうか?』と思っていました。
当時の私と同じ思いをし、心身ともに限界を感じている場合は退職代行サービスの検討をお勧めします。
ブラック企業で勤務している人にしかわからない感覚だと思いますが、ブラック企業では会社を辞めることはとても難しいことなのです。
私自身が会社を辞める際にこのサービスがあれば是非とも使用したかったです。
退職代行サービスとは退職する際に、会社と退職希望者の仲介をしてくれるサービスです。
上司も、働き手も多様化している現代社会らしいサービスだと思います。
本来は、自分で上司に退職の意思を伝えて会社を退職する手続きを行うのですが、会社を辞めることを強引に引き止めるケースが圧倒的に多いです。
私自身も、退職届けを突き返された経験があります。(詳しくはこちらで紹介しています) 退職代行サービスを利用するに当たり、退職代行費として5万を払わなくてはなりません。
それでも退職交渉をする時間と精神的負担を考えたらかなり安いです。
私がブラック企業を辞める際は『ボーナス全額返しても良いから辞めさせてほしい』と言ったこともありました。
ボーナス全額に比べれば安いものだと思います。(実際に返すことはありませんでした。)
退職代行サービスはガーディアンがお勧めです。
ガーディアンは労働組合法人が運営しています。
労働組合は会社と対等に争うことが出来る団体ですので、安心して退職代行をお願いできます。
退職の意思を自分で伝えても上司がわかってくれないときの本当の最終手段があると言うことをわかっているだけでも心強いですよね。
ブラック企業を退職するときに、私のように悩む必要がなくなったというのはとても羨ましい限りです。
会社を辞める際に、会社とのトラブルになることを恐れる人も多いですが、そのようなトラブル解決にも仲介に入ってもらえます。
『会社が損害賠償を払えと言ってくる』『契約違反だ』などと言って会社を辞めさせないブラック企業が存在する今の時代では本当に心強いサービスだと思います。
